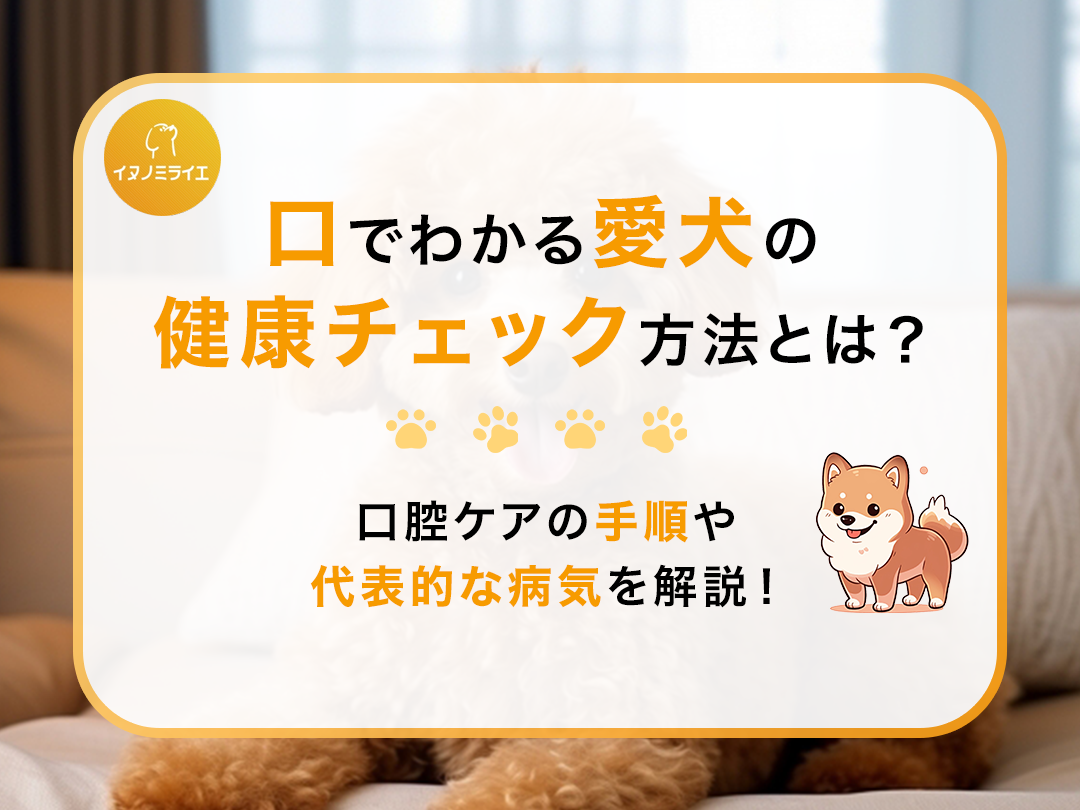
愛犬と遊んだりじゃれたりしたときに、愛犬の口臭が気になる経験をしたことがあるという方もいるのではないでしょうか。愛犬の口臭が臭うときは、口腔内に汚れがたまっていることが多いです。目には見えない内臓疾患とは違い、口の健康は飼い主でもチェックすることができます。
そこでこの記事では、愛犬の口腔内トラブルや口腔ケアについて解説します。愛犬の健康が気になるという方は、ぜひ参考にしてみてください。
犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめ

犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめです。イヌノミライエは、犬用サプリ・健康食品に特化したオンラインショップで、犬の健康面を気遣ったサプリや食品を販売しています。
愛犬が病気になったり、体調を崩す前に飼い主として何ができるかという「予防学」の観点から愛犬の健康を気遣います。ドッグフードとサプリメントを販売していて、愛犬と健康的に楽しい時間を長く楽しんでいきたいという方はぜひ一度イヌノミライエの商品をご覧ください。
【犬の仙豆】

引用元:イヌノミライエ公式サイト
|
給与量/日 |
・5キロ未満 1粒/日 ・5〜10キロ未満 2粒/日 ・10〜20キロ未満 3粒/日 ・20キロ以上 4粒/日 |
|
価格 |
4,980円 |
|
成分 |
・オオイタドリ ・NMN |
※料金は税込です。
犬の仙豆が気になるという方はぜひイヌノミライエ公式の【犬の仙豆】商品詳細をご覧ください。
【項目別】口でわかる愛犬の健康チェック方法

愛犬の口から少しにおいがしたり、歯垢がついていたりする程度の状態なら、歯磨きを行うことで口の中の状態を健康に保つことができるでしょう。
しかし、放っておくと歯周病になる可能性があります。そのため、まずは愛犬を歯ブラシに慣らして毎日歯磨きをするのがおすすめです。
ここからは、口でできる健康チェックの方法について解説していきます。
歯で健康チェック
はじめに、歯から愛犬の健康をチェックしましょう。以下の3つがポイントです。
- 口臭の有無
- 歯石の付着
- 歯のぐらつき
人間と同じで、犬の健康な歯は真っ白でつるつるしています。そのような状態であれば何も心配することはありません。
しかし、犬は唾液がアルカリ性で、食べかすが石灰化してすぐに歯石になることが問題になることもあります。歯石がついてしまうと歯周病の原因となり、全身に悪影響を与える危険があるので注意してください。
よだれで健康チェック
次に、よだれから愛犬の健康をチェックしましょう。以下の4つがポイントです。
- よだれに血がまじる
- 口の周囲をいつも以上に掻いている
- よだれが出るのに食べることができない
- 口に食べ物を入れても飲み込めない
車酔いをしたときや「待て」をするときに、愛犬がよだれを垂らすのは普通のことです。
しかし、いつもと違うよだれを垂らしているときは、それが不調のサインかもしれません。しばらく様子をみても症状が変わらなければ、病院で診察を受けましょう。
また、よだれを垂らしながら痙攣をしているときは、特に深刻です。至急病院に行きましょう。
歯茎や舌で健康チェック
そして、歯茎や舌から愛犬の健康をチェックしましょう。以下の2つがポイントです。
- 歯茎の色が普段と違う
- 舌が白っぽくなっている
口元を触られることに慣れている犬であれば、毎日の歯磨きのときに、歯茎の状態も確認しましょう。
健康な歯茎はきれいなピンクです。しかし、貧血のときは歯茎が白っぽくなります。歯茎が青白い場合は、血液循環に支障をきたしているチアノーゼの可能性があり、呼吸障害や心臓障害を抱えているかもしれません
また、歯茎が黄色い場合には、黄疸の可能性があります。至急獣医師の診察を受けるようにしましょう。
口臭で健康チェック
最後に、口臭から愛犬の健康をチェックしましょう。以下の匂いがする場合は注意したほうが良いかもしれません。
- 腐った卵や生ゴミの臭い
- 便臭
- 酸っぱい臭い
- 甘い匂い
- アンモニア臭
一概に口臭といっても、さまざまな匂いがあります。愛犬に食糞癖があるならば、他に興味を持たせるなどの対策をとって解決しましょう。
酸っぱい匂いは胃腸炎、甘い匂いは糖尿病、アンモニア臭であれば腎臓疾患の可能性があります。愛犬の口臭と照らし合わせて、病気を判断しましょう。
また、犬の健康については、以下の記事で詳しくまとめてあります。あわせて読んでみてください。
愛犬の健康を管理する上でのポイントを徹底解説!部位別、行動別に紹介
犬のよくある口腔内トラブル

健康チェックをして異常を見つけたときには、獣医師の診察を受けましょう。早めの対応で重症化を防ぐことができるかもしれません。
以下で、よくある犬の口腔内トラブルを紹介します。
口内炎

口内炎は口内の粘膜の炎症です。口内の粘膜は新陳代謝が早く、傷は早く治りやすいです。
しかし、口内は常に唾液で湿って温かく、細菌感染が発生しやすいです。そのため、口内炎のできた粘膜は、食べ物との接触で痛みが発生する可能性があるのです。
以下で原因、症状を紹介します。
原因
犬の歯についた歯垢・歯石に含まれる細菌が刺激となって、口腔粘膜に炎症が起きます。また、異物を口にして口腔内に傷ができたりすることで、口内炎ができることもあります。
症状
口内炎になると、歯茎や舌、口の中の粘膜が赤くただれることがあります。また、白い水疱のようなぷつぷつや膨らみが現れ、愛犬自身も症状を気にするようになります。
その結果、前足で口の周りをこすったり、掻いたりするなど、口を気にする仕草が頻繁に見られるようになるでしょう。愛犬に似た症状がないかどうか確認してみてください。
検査方法
獣医師に口腔検査をしてもらい、口内炎か歯肉炎かを見極められます。ただの口内炎ではない可能性がある場合には、口内炎周辺の組織片や組織を採取し生検に出すことで、腫瘍などとの区別をします。
なかなか治らない場合は、もっと深刻な病気が隠れているかもしれません。その場合は、血液検査を行い、腎臓病や細菌感染症などの基礎疾患の有無を調べます。
乳歯遺残

乳歯の生え変わり時期を過ぎても、乳歯が残ってしまうことを乳歯遺残といいます。通常、乳歯は生後3ヶ月あたりから抜け始め、7ヶ月あたりで永久歯が生え揃います。しかし、乳歯遺残になると乳歯が残ってしまいます。
以下で原因、症状を紹介します。
原因
犬や猫は永久歯が生えてから乳歯が抜けます。そのため、乳歯と永久歯が同時に揃う時期もあります。通常、永久歯が生える頃に乳歯の根がだんだん溶けていき抜け落ちます。しかし、犬歯は根がしっかりしていて、乳歯が抜けずに残ってしまうのです。
症状
本来は1本の歯が生える場所に、乳歯と永久歯が2本並んで生えてしまいます。そのため、歯が生えている位置や向きがずれている、歯の形が多少変形しているなどの症状がみられるでしょう。
また、乳歯と永久歯が重なり合っている部分は、特に歯垢・歯石が落としにくいので歯周病になりやすくなります。入念に歯を磨くようにしましょう。
検査方法
乳歯遺残は、見た目でも確認しやすいです。しかし、乳歯と永久歯が判別しにくい場合や、乳歯の歯根部の状態を確認したい場合には、歯科用レントゲン検査が必要です。
怪しいと感じたら、必ず愛犬を医療機関に連れて行くようにしましょう。歯周病

歯周病は、犬の口腔トラブルで最も多いといわれます。歯周病の中でも、主に初期段階を「歯肉炎」、症状が悪化すると「歯周炎」と呼びます。
歯周病は歯茎の下の部分でよく起こるため、病気が進行するまで気づかないことが多いです。そのため、定期的なチェックを心がけましょう。
原因
口の中の細菌が歯垢を形成し、それが歯の表面に付着することで歯周病が始まります。唾液の中のミネラルが歯垢を硬化させて歯石にし、歯にしっかりと付着します。
細菌である歯石がかたまることで、放置すると歯周炎が進行してしまうのです。症状
初期の歯肉炎段階では口臭、歯茎の赤みや腫れの症状がみられます。症状が進行して歯周炎になると、顎の骨(歯槽骨)などの歯の周囲の組織まで炎症が進み、歯槽骨が破壊されてしまいます。
歯周炎がここまで進行してしまうと、歯が支えきれなくなりぐらぐらして、最悪の場合抜け落ちてしまうかもしれません。検査方法
大抵の場合、目視で診断がつきます。しかし、進行状況を把握するにはレントゲン検査や歯周ポケットにスケーリング器具を差し込み、歯周ポケットの深さを測るプローピングが必要です。
口腔内腫瘍

歯肉や舌、口の粘膜などにできる腫瘍のことをいいます。
腫瘍には、主に2種類あります。細胞が過剰増殖してその場にとどまるだけの良性腫瘍と、体に悪影響を及ぼす悪性腫瘍の2種類です。
悪性腫瘍では、最終的にがんになります。犬の口腔内腫瘍は、腫瘍の約 4%を占めます。そのうち約 90%は悪性腫瘍です。
原因
残念なことに、口腔内腫瘍になる原因は突き止められていません。
症状
口腔内腫瘍は痛みを引き起こしやすいです。動物は痛みを感じるとき、たくさんのよだれを垂らします。
また、食べるときに痛みが生じるので、だんだんと食欲がなくなります。 さらに、「口臭がきつくなる」「硬い物を食べると出血する」「口の片側だけで食べ物を噛む」などの症状を確認できるようになったら口腔内をチェックしてみましょう。
検査方法
まずは触診や目視で確認します。次にリンパ節の触診やレントゲン検査を使用して、犬の腫瘍が転移していないかどうか確認します。また、似たような症状を示す他の病気を否定するために、血液検査や超音波検査も行うかもしれません。
他の病気ではないことが分かったら、腫瘍の一部を切り取る針吸引生検を実施します。これにより犬の口腔腫瘍の種類を判断し、どのような病気かを確認できるのです。
ただし、針吸引生検では判別がつかない場合もあるため、注意が必要です。
定期的なお手入れが大切!愛犬の口腔ケア方法

人間同様、健康で長生きするために口腔ケアは非常に重要です。食べることは生きる上での楽しみでもあり、飼い主と愛犬の信頼関係を深める大切な時間でもあります。
しかし、毎日の食事で歯垢はたまります。そのため、毎日口のケアを続けることが健康につながるのです。
以下で、詳しい口腔ケアの方法を紹介します。
口周りを拭く手順
愛犬の口周りには、食後に水や食べ物がつくことがあります。特にあご下は、なかなかみづらいです。
しかし、汚れたままにしていると匂いや毛玉の原因になります。そのため、ウェットシートやコットンやタオルでやさしく拭いてあげましょう。
また、口の上の部分は鼻側から口角に向かって左右それぞれを優しく拭いていきます。あご下も忘れずに、あごから首に向かって優しくなでるようにきれいにしましょう。
歯磨きの手順
歯磨きが苦手な犬は多いですが、少しずつ慣らすことで毎日の歯磨きが習慣化されるでしょう。
まずは、指サックで歯全体の汚れを落とします。指サックの方が歯ブラシよりも異物感が少ないため、歯ブラシに慣れる準備としても使いやすいです。
また、指の腹を横に滑らせて歯全体の汚れを落とします。歯石がつきやすいのは、歯と歯茎の境目です。
歯ブラシは鉛筆をもつように持ち、力をいれすぎないように優しく磨きましょう。大きな犬歯を上下左右に優しく磨き、その後切歯(前歯)を磨きます。切歯は小さいので左右に磨けば十分です。最後に、歯ブラシを口角から滑り込ませて奥歯を磨きましょう。
まとめ

大切な家族の一員である犬の健康を守るためにも、口腔ケアは定期的に行いましょう。犬は口元を触られることを嫌がるので、子犬の頃からの習慣にするのがおすすめです。
愛犬とできるだけ長い時間を過ごすためにも、健康チェックは怠らないようにしましょう。この記事を参考に、適切な方法で愛犬の口腔ケアをしてみてください。
犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめ

犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめです。イヌノミライエは、犬用サプリ・健康食品に特化したオンラインショップで、犬の健康面を気遣ったサプリや食品を販売しています。
愛犬が病気になったり、体調を崩す前に飼い主として何ができるかという「予防学」の観点から愛犬の健康を気遣います。ドッグフードとサプリメントを販売していて、愛犬と健康的に楽しい時間を長く楽しんでいきたいという方はぜひ一度イヌノミライエの商品をご覧ください。
【犬の仙豆】

引用元:イヌノミライエ公式サイト
|
給与量/日 |
・5キロ未満 1粒/日 ・5〜10キロ未満 2粒/日 ・10〜20キロ未満 3粒/日 ・20キロ以上 4粒/日 |
|
価格 |
4,980円 |
|
成分 |
・オオイタドリ ・NMN |
※料金は税込です。
犬の仙豆が気になるという方はぜひイヌノミライエ公式の【犬の仙豆】商品詳細をご覧ください。
また、犬の健康に関する下記記事もあわせて読んでみてください。
▼あわせて読みたい


