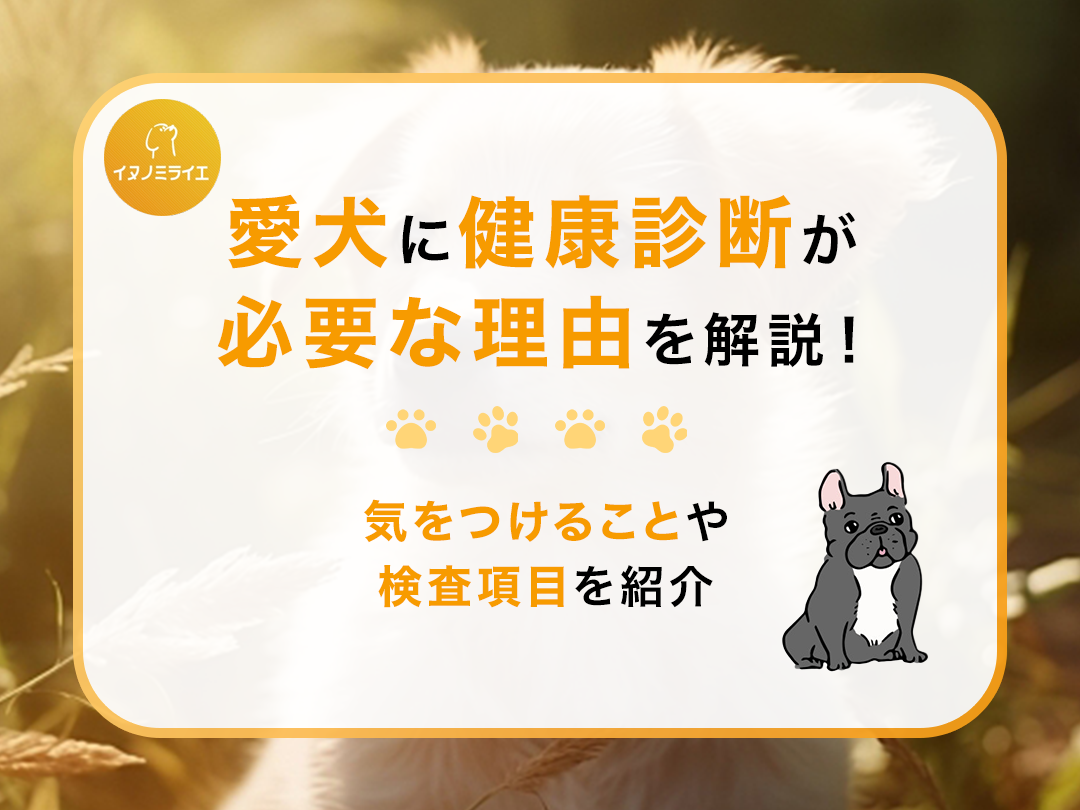
健康診断は、病気の予防や早期発見のために必要です。人間と同じように、動物にも感染症や病気が増えています。
しかし、人間と動物では健康診断の内容が違います。愛犬に健康診断を受けさせようと考えていても、なかなか踏み出せないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、愛犬の健康診断の際に気をつけるべき点について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめ

犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめです。イヌノミライエは、犬用サプリ・健康食品に特化したオンラインショップで、犬の健康面を気遣ったサプリや食品を販売しています。
愛犬が病気になったり、体調を崩す前に飼い主として何ができるかという「予防学」の観点から愛犬の健康を気遣います。ドッグフードとサプリメントを販売していて、愛犬と健康的に楽しい時間を長く楽しんでいきたいという方はぜひ一度イヌノミライエの商品をご覧ください。
【犬の仙豆】

引用元:イヌノミライエ公式サイト
|
給与量/日 |
・5キロ未満 1粒/日 ・5〜10キロ未満 2粒/日 ・10〜20キロ未満 3粒/日 ・20キロ以上 4粒/日 |
|
価格 |
4,980円 |
|
成分 |
・オオイタドリ ・NMN |
※料金は税込です。
犬の仙豆が気になるという方はぜひイヌノミライエ公式の【犬の仙豆】商品詳細をご覧ください。
犬に健康診断が必要な理由

犬に健康診断が必要な理由として、以下の4つが考えられます。
- 犬は人間の4倍のスピードで老いるから
- 犬も高齢化が進んでいるから
- 犬は不調を声に出すことができないから
- 犬は年をとると免疫力・筋力が低下するから
はじめに、人間は1年に1回誕生日を迎えますが、小・中型犬の場合は1年で4歳、年を取ります。そのため、老いるのが早く病気のリスクも高まります。
2つ目に、人間も高齢化社会と言われていますが、犬の平均寿命も上昇しています。それに伴い病気にかかってしまう犬が増えています。そのため、病気の早期発見のために犬の健康診断が必要なのです。
人間と違って犬は不調でも言葉にする事ができません。定期的に健康診断をすることで安心につながります。さらに、免疫力や筋力の低下が加齢とともに現れます。シニア期を迎えた犬の場合、ウイルスや感染病を防ぐためにも健康診断がとても重要なのです。
犬の健康診断の検査項目

犬の健康診断の検査項目は、以下の7項目があります。
- 問診
- 視診、触診、聴診
- 血液検査
- 尿・便検査・レントゲン検査
- 超音波検査
- MRI検査
それぞれ検査内容が異なり、発見できる病気や感染症も異なります。検査内容について詳しくみていきましょう
問診
問診は、愛犬の状態を動物病院へ伝える事です。問診では、普段から愛犬の普段の生活をしっかりと観察して、正確な情報を伝える事が重要です。
視診、触診、聴診
視診は、愛犬の状態を獣医師が目で直接見る診療です。また、直接触る場合もあります。痛い箇所はないかなどをチェックをすることができます。そのため、普段から人に触られる事に慣れておくと良いでしょう。触診の際に、犬と獣医師の距離が近くなるので、臭いで異常を発見することもあります。
聴診では、心臓の音や肺の音に異常がないかを調べることができます。
血液検査

人間と同じく、血液検査をする事で内臓の状態を獣医師が把握することができます。血液検査の数値異常がわかることで、病気の早期発見につながります。
尿・便検査
尿、便の検査により犬の体内に異常がないかを確認します。尿・便検査の結果、愛犬の体内に寄生虫がいるかどうかもわかります。
病院にもよりますが、健康診断の日の朝に出した尿や便を持参する場合が多いです。
レントゲン検査
レントゲン検査をする事で、犬の健康状態がとてもよく分かります。
内臓はもちろん、骨に異常がないかなど、レントゲン検査によるチェック項目の範囲はとても広いです。そのため、1回の検査でさまざまな項目をチェックすることができます。
超音波検査
超音波検査は、愛犬に負担のない検査です。麻酔をすることもありません。超音波検査により、内臓や血液に異常がないかを調べることができます。
MRI検査

MRI検査は、すべての動物病院で行われている検査ではありません。
脳の異常を発見することが目的ですが、ほとんどの健康診断では行われない検査です。愛犬の脳に異常がないか気になる際は、獣医に依頼することをおすすめします。
また、犬の健康管理について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて読んでみてください。
愛犬の健康を管理する上でのポイントを徹底解説!部位別、行動別に紹介
愛犬の健康診断で気をつけること

愛犬に健康診断を受けさせる際に、気をつけることは複数あります。ここでは、以下の5つについて紹介します。
- 事前に検査内容を確認する
- 覚えやすい時期に受ける
- 初めての健康診断は生後6ヵ月ごろに受ける
- 検査項目によっては絶食が必要な場合がある
- 服用している薬がある場合は申告する
それぞれみていきましょう。
事前に検査内容を確認する
愛犬の年齢や種類によって、検査内容が変わります。シニア犬となれば、子犬の頃よりも検査をする内容が増えます。
そのため、検査内容を事前に確認をすることがとても重要です。事前に獣医師と相談をすることで、細かい検査内容について聞くことができるでしょう。
覚えやすい時期に受ける
愛犬の健康診断を受ける時期をうっかりわすれてしまう事例も少なくはありません。
そのような失敗をなくすためには、覚えやすい時期に受けると良いでしょう。例えば、愛犬や家族の誕生日等が該当します。
覚えやすい日付で健康診断を受けるようにすることで、忘れずに毎年受けられるでしょう。
初めての健康診断は生後6ヵ月ごろに受ける
初めて犬を飼う方の中には、はじめての健康診断はいつなのか分からないという方も多いです。きちんとした決まりはありませんが、生後6ヶ月までが望ましいです。
検査項目によっては絶食が必要な場合がある

健康診断の内容によっては絶食が必要となる場合もあります。例えば、レントゲン検査の前や血液検査の前は絶食が必要です。なぜなら、食事が検査結果に影響しやすいからです。
一方、水分を与えても良いのか疑問に思う方も多いです。水分に関しては、特別な指示がなければ基本的に大丈夫です。しかし、自己判断はせず、獣医師の指示に従うようにしましょう。
服用している薬がある場合は申告する
健康診断では、自己申告が必要な事柄がいくつかあります。その中の1つが、愛犬が現在服用している薬です。食事の場合と同じく、健康診断の前には薬の服用を止められる場合があります。
愛犬の持病などによっては、薬の服用を止めてはいけない場合もあるので、きちんと獣医師と話し合うことが大切です。
犬の健康に関するよくある質問

最後に犬の健康診断に関するよくある質問について解説します。犬の健康診断でまだわからないことがあるという方は、最後にここで疑問を解消してください。
愛犬の健康診断は何歳から?
愛犬の健康診断は、生後6ヶ月頃からがおすすめと言われています。健康診断を小さな頃から受けさせることで、先天的な病気の発見にもつながります。
また、犬種によっては心臓病にかかりやすいこともあります。愛犬の異常にいち早く気づくためにも、早いうちから健康診断に連れていきましょう。
愛犬の健康診断の頻度はどのくらい?
愛犬の健康診断の頻度は、基本的に1年に1度受けることが推奨されています。
さらに、シニア犬の場合は半年に1度の頻度での健康診断が理想です。ここで言うシニア犬とは、小型や中型犬なら7歳程度です。大型犬なら5歳程度です。
シニア犬は年をとるのが早いため、より頻繁に健康診断に連れて行く必要があります。
愛犬の健康診断の費用はどのくらい?
愛犬の健康診断の費用は、動物病院によって異なります。また、住んでいる地域や検査項目によっても異なります。そのため、はっきりと数字を出すことはできません。
基本的な金額は5,000円から3万円です。動物病院にあらかじめ費用を聞くことで、安心して健康診断を受けられるでしょう。
まとめ

この記事では、愛犬の健康診断の必要性について紹介しました。
人間の健康診断と同じように、犬にも健康診断が必要です。また、検査を受ける時期や費用について、事前に獣医師と話し合いをすると良いでしょう。費用に関しても、安心して健康診断を受ける事が大切です。
この記事で紹介した検査項目をしっかり把握し、愛犬の症状にぴったりな治療を選択しましょう。
犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめ

犬用サプリ・健康食品を購入するならイヌノミライエがおすすめです。イヌノミライエは、犬用サプリ・健康食品に特化したオンラインショップで、犬の健康面を気遣ったサプリや食品を販売しています。
愛犬が病気になったり、体調を崩す前に飼い主として何ができるかという「予防学」の観点から愛犬の健康を気遣います。ドッグフードとサプリメントを販売していて、愛犬と健康的に楽しい時間を長く楽しんでいきたいという方はぜひ一度イヌノミライエの商品をご覧ください。
【犬の仙豆】

引用元:イヌノミライエ公式サイト
|
給与量/日 |
・5キロ未満 1粒/日 ・5〜10キロ未満 2粒/日 ・10〜20キロ未満 3粒/日 ・20キロ以上 4粒/日 |
|
価格 |
4,980円 |
|
成分 |
・オオイタドリ ・NMN |
※料金は税込です。
犬の仙豆が気になるという方はぜひイヌノミライエ公式の【犬の仙豆】商品詳細をご覧ください。
また、犬の健康管理について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて読んでみてください。
▼あわせて読みたい


